ミュージック・ケア?
ABOUT
-
ミュージック・ケアとは
音楽の特性の一部を利用した、その人がその人らしく生きるための援助活動です。子どもの場合はその子どもの持っている力を最大限に発揮させ、発達の援助を行います。

-
ミュージック・ケアのねらい
音楽の特性を生かして、対象者の心身に快い刺激を与え、対人的な関係の質を向上させ、情緒の回復や安定を図ります。
さらに、運動感覚や知的機能の改善を促して、対象者の心身と生活に好ましい変化を与えます。

ミュージック・ケアの主な効果
Effect
安心できる場と関係性を獲得し、生活意欲の喚起や助長、向上へとつなげ、生活全領域にわたって好ましい効果をもたらします。
- 関係性の発見と改善
- 不安行動の軽減
- 発達の促進
- 集団参加の促進
- コミュニケーション
- 自己コントロール
- リラクゼーション
- 注意集中力
- 情緒の安定
- 身体機能の促進
- 生きがい
- 介護予防
- 身体運動の誘発
- リハビリ効果・発達援助
- 歌唱による効果
- 昔のことを思い出す(回想)・呼吸を整える・言葉の誘発
- 楽器演奏
- 発達援助・機能訓練

ミュージック・ケアの主な対象者
Target Person
赤ちゃんからお年寄りまで、障がいがあってもなくても、どんな人も対象になります。
-
発達の援助
知的障がい・ダウン症・自閉症・情緒障がい・精神障がい・言語障がい・視覚障がい・脳性マヒ・重症心身障がい・強度行動障がい・重複障がい
-
心身のリハビリテーション
認知症・リハビリ
-
元気な人づくり(保健事業)
子育て支援・心の教育・元気な人づくり・フレイル予防

ミュージック・ケアの方法
Method
| 基本メソッド |
オリジナル曲・クラシック・ポピュラー曲などを含み、ミュージック・ケアのオリジナル基本メソッドとしています。これらの曲には、発達援助や身体機能促進の観点で作られた基本動作と基本姿勢(キーポジション)が組み合わされています。(約100曲) |
|---|---|
| 身体表情表現 |
心と体はつながっていることから、相手の気持ちを言葉ではなく、情動で伝え合うものです。 ボディーランゲージとしての役割を果たすものでもあります。 発達援助・機能訓練としても役に立ちます。 |
| 歌唱 |
懐メロ・唱歌・民謡などを取り入れ、昔のことを思い出す(回想)・呼吸を整える・言葉の誘発としても役に立ちます。 |
| 楽器演奏 |
音楽技術を高めるための訓練として行うのではなく、音楽をより積極的に楽しむために利用します。 そのために、メロディー楽器よりも打楽器などを主に使用します。 |
| その他の道具の使用 |
聴覚だけでなく、視覚・触覚・嗅覚などを刺激し、音楽を楽しみます。 音楽を感じてもらうために、シャボン玉・フラップバルーン・ボール・紙・ボード・ビニール袋などを利用します。 また、音楽を伝える手段として、タッピング・マッサージ・見せて・触って風を感じて などの方法を利用します。 |
| 即興プログラム |
その場で集団を観察し、対象者の気分やリズムに合わせ、対話をするように即興でプログラムを組み立てていきます。 セッション全体をひとつの曲として見立てて、最後には静かで心が落ち着き満足感を持って、快い余韻を残すような曲で終わるように組み立てます。 |
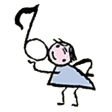
ミュージック・ケアをするにあたって
自らが選び、自らが決定し、自らが行動するということを大切にします。
自らがしてみたいと思える気持ちを育てます。
する人、される人という区別をするのではなく、ケアされあう関係を大切にします。
音楽性や音楽的技術を身につけることはもちろんですが、豊かな人間性、生き方なども大切にします。
効果を急がず、たくわえと待ちのセラピーです。
ミュージック・ケアの場は、何かを無理矢理させたりするのではありません。
何かが上手にできたり、人よりも先に何かができるようになることでもありません。
今のままのあなたを受け止めるところからはじまります。
そして、自らが自分らしく成長しようと思うまで、そっと寄り添います。
さらに、自らが何かをしてみたいなと思ったとき、手を差し伸べて援助するのです。
もう一度本当に人間本来の穏やかで、生き生きと生きようとする気持ちを支えてあげるところです。
そして、共にケアをしあいながら豊かに成長しあう場なのです。